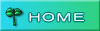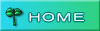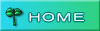20. カリスマ的哲人の生きざま
田 隅 本 生
大学の職場で私が三木先生と直接的関係をもっていたのは昭和三七年の春からまる五年間のことだから、もう遠い昔のことになる。その時まで私は動物学の学生だったのだが、たまたま縁があって東京医科歯科大学歯学部の解剖学教室に助手として奉職することになった。お茶の水の医歯大ではそのころ、歯学部解剖学教室(二講座)と医学部解剖学教室(当時二講座)が古い建物の二階に共存していた。解剖学教育に関しては、これらは同じ学部の同じ教室であるかのように、何事にも共同で当たっていた。学部間のカベはほとんどなかった。講義や実習という教育面から離れたところでも、そこのスタッフは互いに往来し、自由に交流していたのである。
そこでまもなく私は、一室をへだてた医学部解剖の小さな研究室の主は、助教授の三木成夫という方だということを知った。医学部の先生としては一風変わった、俗気のまったくない、ある種の崇高ささえ備えた人だったということは衆目の認めていたところで、かげで人々は「おミキさま」とか「ミキナリさん」とか呼んでいた。しかし、何かわからないが、ウックツした想念を抱いておられる様子が誰にも見てとれた。三木さんは私より十年年長だから、そのころまだ三十七ぐらいだったことになる。
三木さんと、歯の教育研究に携わっていた私とには研究面での一致点は少なかったが、ときどき雑談をするうちにやがて、三木さんは俗界の名利や力関係などには全く興味がないかわり、古典的な芸術や科学、とくに比較形態学の関心が深いこと、鋭い造形的センスの持ち主であること、異常に鋭敏な感受性と洞察力をもっておられること、などがわかってきた。
同じ事柄でも三木さんの心の琴線にふれるときは、凡人より何倍も強く感動され、そのわけの深遠さに畏怖を覚えることがよくあった。思い出すままに、その例をいくつか挙げてみよう。
後年になって三木さんが出された『胎児の世界』(中公新書)の中に次のようなくだりがある。
「古生物学の世界が何かやむにやまれぬ現実となって、急速にわたくしの中に広がりはじめていた。……動物学専攻(=出身)のT君がいつもの真摯な表情でやって来たのはそのころだ。一冊の本を手にしている。『ジョセフ・ニーダムが一九三〇年にどうも同じことを言っているそうですよ。』わたしは脳天に一撃をくらう。……ヤラレタ!わたくしはものの見事な空気投げをくらった気持ちになる。……」このT君というのは実は私のことで、一冊の本とは、E・ボールドウィン著『比較生化学入門』(みすず書房刊)という小冊子だった。そのとき私は鈍感にも、三木さんがこれほど深甚な衝撃を受けられたとはつゆ思っていなかったのである。
それより前のことアメリカの A.S.Romer の Vertebrate Paleontology(「古脊椎動物学」旧版)という名著を三木さんに紹介したことがあった。「古生物学の世界が広がりはじめた」のには、この本がきっかけの一つになったのだと、私は推測しているのだが、これは思い上がりであろうか。
今は思い出すのも気恥ずかしいことながら、そのころ私は無謀にも E.H.Colbert の Evolution of the Vertebrates という本の和訳の仕事を進めていた(その完成には五年もかかった)。これは『脊椎動物の進化』(旧版、上・下、築地書館刊)として出来上がった。その上巻の見本を受けとったとき、私は三木さんを訪れ、こんな本になりましたよ、とお見せした。三木さんはそれを手に取ってパラパラめくるなり忽ち興奮し、「いま、これをくれろ!」と言って放さない。それは“見本”だったから私はただ「見せる」だけのつもりだったのだが、三木さんのその性急な執着ぶりに気押されて、そのまま差し上げてしまった。「恵存」と書きもせずに。さっそく巻き上げられてしまったのだ。そのあと下巻ができたとき、追加して一部進呈したことは言うまでもない。拙訳ではあっても、この訳書が三木さんの“過去への回帰”に何らかの影響を及ぼしたことは確かだろうと、私はひそかに自負している。
これと似たことがもう一度あった。何の機会だったか、私がもっていた X.Bichat の Recherche physiologique sur la vie et la mort(「生と死の生理学的研究」、一八〇〇年)の復刻版を三木さんに見せたことがある。三木さんはそれをわしづかみにするや、血相を変え、両手を震わせながらどなったものだ。「こ、こ、こんなもの、どこで手に入れた?!」その時は“没収”されずにすんだ。この本はやがて、当時三木さんがおられた解剖学第三講座の研究室で、萬年甫教授、三木さん、平光厲司博士、私など数名のグループによる輪読会のテキストに使われ、それはかなり長く続けられた。
そののち何年かたって、驚いたことに三木さんは東京芸術大学に移られ、水を得た魚のように豊かな著述活動を開始された。エッセイ、連載物、単行本などの形で現れた多数の著作はすべて、万華鏡のように多彩で、洒脱で、生命界に関する奇想天外の洞察に満ち、独特の世界へ読者を引きずりこむふしぎな力をもっている。かつて私が日常的に交わっていたころには漠然と感じていただけの三木さんの精神活動が、これらの著作を読んで初めて具体的にわかるようになった。私は一別以来ほとんど会っておらず、遠く離れてテレパシーをしていただけなのだが、くり返して反芻するうちに、あらためて三木さんへの“見直し”をすることとなったのである。
何年か前、私はS.J.グールドの『パンダの親指』(桜町翠軒訳、早川書房刊)の中で「熱狂のランドルフ・カークパトリック」という章を読み、強い感銘を覚えたことがある。ちょっと長いが、その一部を引用させていただこう。
〔第一次大戦の少し前、ランドルフ・カークパトリックは医師を廃業して博物学に転業し、大英博物館で主にカイメン類の分類の研究者になった。彼はある日、巨大有孔虫の化石である「貨幣石」を火山岩の中に偶然“発見”したのち、さまざまの岩石につぎつぎに同じものを認め、ついにあらゆる岩石がすべて貨幣石で出来ているとまで考えるに至った。〕それでもまだカークパトリックは飽き足りなかった。彼は、自分がさらにもっと根源的なものを発見したと考えていた。地殻や隕石だけでは満足せず、貨幣石の渦巻き状の形を、生命の本質の表れ、生命そのものの構造だと考えるようになったのだ。ついに彼は自分の考えを極限まで押し広げた。…岩石や貨幣石やそのほか生あるものはすべて、「生命物質の基本構造」、あらゆる生存物のラセン形態の表れなのだ、というのである。……頭がおかしかったのか。そうだろう(ただし、彼がDNAの二重ラセンを直感していたのだと考えないかぎりで)。それとも霊感がひらめいたのか。そうに違いない。……彼は、総合を目ざす盲目的な情熱と、本質的にまったく異なる物事を同列視するような想像力とを兼ね備えていた。外形の類似は必ずしも共通の源をもつことを意味しないという真理を無視しつつ、彼は……形態の類似を一貫して捜し求めた。彼はまた、自分の観察からというより、自分の願望から類似性を築き上げたのだ。にもかかわらず、大きな総合を目ざす粗雑な探求が、冷静な科学者にはまったく思いつかないような真の関連性をあばき出すことがある。……彼らの考えが正しいときには、ずばぬけて正しいために、彼らの洞察は、普通の科学者が普通の方法で行う地道な仕事を貧弱なものにしてしまう。……
私がこれを読みながら二重写しに連想したのはまず三木さんのことである。著者の認識の鋭さもさるものながら、時代と国と文化の違いをこえて、これほど三木さんを彷彿させる話はめったにないと思う。
本の話が続いて恐縮だが、昨年私はイギリスの古生物学者、B・ホールステッドの『「今西進化論」批判の旅』という変わった本を読んだ。これは今西錦司氏の進化論を論評したものだが、そのついでに今西氏と、古生物学者の井尻正二氏とを対照的人物として取り上げている。そして、両氏とも、その学問上の教説を必ずしも理解しないまま追随信奉する人々、つまりファンを無数にもっている、という鋭い指摘をしている。言いかえれば、これら両氏は、科学界にはまれな「カリスマ」なのだ。私はこうした結びつけを、この本に書かれるまではっきり意識していなかった。そして私は、三木さんのことに、またカークパトリックのことに思い及んだ。三木さんは一種のカリスマだったのだ。
このように把えてみると、カリスマ的学者たちの共通性が浮かび上がってくる。まずこれらの人々はワガママである。彼らは、虫や鳥や魚などを狙って遊び呆けていた少年時代の心を、変質させながら一生持ちつづける。精神の“幼形”を維持しながら“成熟”するのである。“科学的”にみれば、その言説には明らかな誤りやあやしげな独断論が散在していても、当人にとってはそんなことは大した問題ではない。初めから独自の体系をなす世界をもち、それに触れる微かなきっかけに鋭敏に反応し、直感によって深い洞察に達する。そして、それを雄弁に表現する。判断の理由の説明、文献の列挙などの七面倒な手続きは全部省略して、ただ結論だけを述べる。こうして凡人はその言説を理性的には十分納得できないまま、情熱的共鳴を覚える結果となる。わがままな当人の側では、自分の考えが他人にはよく呑みこめないことなどどうでもよいのである。
三木さんには解剖学者、生物学者、教師、医師、美術家、名文家などのさまざまな側面があったが、本領はそういうところにあったのではない。また、“三木派”のリーダーだったわけでもない。三木さんの本質は、からだと心の歴史的理解に没頭した、カリスマ的“自然科学者”だったのである。