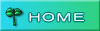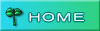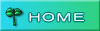64. 師の影を踏まず
中尾 喜保
それは三十年余り前の北風の吹く寒い晩であった。やや前かがみになって谷中の墓地を日暮里駅へと急いでいた時、三木先生が「あんたは歩く時の姿勢が悪いな−、昨日もラブレーン=寛永寺と博物館の間の静閑とした径を二人はそう呼んでいた=を学校へ急ぐ姿を見掛けたが同じ様に背を丸めていたぜ、M.erector
spinae を忘れたらあかんがね」と、例の口角を僅かに引き上げたミキ・スマイルを浮かべながら私の腰をさすられた。横文字の出てきたのは、当時三木先生と二人で、東大の三階の寒々とした解剖実習室で、固有背筋の走行と支配神経の末端を端念に剖見しながら、そろいのB3のクロッキー帖に、背筋の表層から深層の短い筋に至るまでを、夜遅くまでスケッチしていた時期で、その間は脊柱起立筋群に関係する話を手当たり次第にかわしながら知識の深さを競い合っていた時で、ウインザ・チェアーと背筋の関係が話題になっていたからである。揃いの画帖といったのも、いわくのある話で、とにかく三木先生は非常な凅り性で、紙・鉛筆に至るまで、自身の機能に合った適切なものでない限り駄目という体質で、二人してやっと見つけた画帖であったからである。
後年、三木先生が芸大へ移籍されてから、奈須高原にある研究機関で毎年美術解剖学講座の教官が、院生達と三泊ほどのゼミをするが、黒磯の駅につくまで、二人で諸もろのことを綿めんと話すのが常であった。先生最後のゼミであったが、その時の話では、模式図を描く筆を自分で作ってそれを如何に大切に使っているかを身振り手振りで語り、話が東大の解剖室でのスケッチの昔に戻って、「あの時は筆が滑らなくてへばったぜ」と讃岐なまりで話していたが、異常といえなくもない程の凅り性で、それは持物ばかりでなく、話の内容にまでも及んでいた。
きて、話は私の姿勢に戻るが、なるほど指摘を受けた通り、項垂れた姿の影がくっきりと歩道に落ちていた。どちらともなく影が道路の凸凹に馴染んで、様ざまな形に変わってゆくことにからんで、私はデホルメの面白さや影の色は黒でなく蒼と教えるべきだと語り、三木先生はゲーテのファルビーゲン・シャッテンは月夜を彷徨した体験が生んだ言葉だと話されていた。私はその夜の空の見事な蒼さから、出藍の誉れの“青”について、かつて大村西涯先生は群青の美しさは雨過天晴の空の色が基で、村雨の後の満月の夜空の蒼きであると講義されたとか、広川松五郎先生は「この言葉は理論としては云い得て妙であるが、画家なら当然紅蓮の焔の朱にするであろうに、何故青なのか」と語られたが、私は朱の華やかさより矢張り青が諺の真意を伝えるのに適している。何故なら、出藍の誉れという諺は表裏二つに解することができるのではないか、表は読んで文字の通りで、藍から抜け出た青の見事きを讃えたものであるが、今一つは青の誉れの裏にひそむ老のなげき……積年の知識といえども老耆将に之を越ゆの諺通り、追い抜かれた者の表に出し得ない一抹のなげきを現すのに、青と藍という関係と、朱の華麗さよりも青の深みを持ってきたところに、師の心の疼きを暗示したセンスの良きと、自然の事象を引用する観察の豊かさに感心すると話した時、三木先生は突然「三尺下って師の影を踏まずとは、まさにその老師の心にしのびよる“ごう”の疼痛を鎮めるために、弟子がとらねばならぬ心がまえを述べたもので、師と弟子の両者の心に極く自然にわいてくる心根が、将来離反の源になるところが、これまた“ごう”の世界やな−、困ったことにこれらの感情は知識で理解でき得るものではなく、実感として感じた時にほんまものになるんぜ」とさとされた。勿論この話は富永先生のお話だという註をつけてではあるが、しかし、この夜の問いかけは三木先生なればこその私への戒めであると思っている。
何故こんな戒が出藍から生まれたかといえば、当時、私は恩師であった西田正秋先生と、以前の様にしっくりと行かなくなっていて、その悩みを三木先生に訴えたことがあった。その時はただ黙って聞いてくれただけで、教訓めいた事は何もいわれなかったが、今にして思えば、私の話の中から、弟子としてあるまじき何物かを感じられていたのかも知れない。その風の吹く夜の会話は「まあ、あんたも自分が西田先生と同じ立場になった時に始めて、今あんたが不条理と感じていることの、可か否かを実感として感じるのやないか」で終わってしまっていた。
かつて、三木先生から忠告された“師の影を踏まず”の戒が、指摘された通り実感として体感できる年となっている。三木先生は天国で、膝を少し曲げ、片手を頭まで上げた最も三木先生らしいポーズで、「やあ実感しおったか」と語りかけてくださるに違いない。