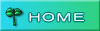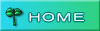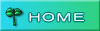80. モーツァルトとジョゼフ・ニーダム
井上昭夫
“あのモーツァルトが十九才まで自分のウンコを練っていたんですか”と深くうなずきながら三木先生はいたく感銘された様子である。天理での講演が決まっていた前日の夕方、私は天理駅に先生を迎えに出た。そこで偶然、二十数年ぶりにイギリスのジョン・ニューマン君と出会った。ニューマン君はいまを去る二十数年前天理大学で柔道を学び、現在はBBCの日本語部長の任にある。宿舎が同じだというのでニューマン君にも車に同乗してもらって、三十八母屋という天理のゲストハウスに向かった。モーツァルトのウンコの話は、その日の夕食であるフランス料理を賞味している時に、ニューマン君の口から突然出た。三木先生にとっては全くの新しい、うれしい情報であったにちがいない。その証拠に三木先生はこのモーツァルトの話を、亡くなられるまでいろんだ人達にしておられたと聞く。この話は、御存知、同じく芸大の名物教授であった野口三千三先生が、彫刻家の第一歩は腸感覚を両手に取り戻すことであり、それには自分のウンコをこねるのが一番ということから、学生にそれを実践させているという、有名な話にあいなったあとのハプニングであった。彫刻家だけでなく、一流の音楽家にも通じる芸術上の真理として、ウンコをねることの国際的普遍性に感嘆されたのかも知れない。この時のウンコの話は、生態学から宇宙論にまで展開されて延々と続くのだが、今回はこの位にしておこう。
さて、三木先生と私の出会いはたしか昭和六十年頃であったと思う。私は天理から上京の途中、京都のある本屋に立ち寄った。中公新書の並びに眼を走らせていて、最初に自然に手がのびてペラペラと頁をめくった本が『胎児の世界』三木成夫著という一冊であった。
“過去に向かう「遠いまなざし」というのがある。人間だけに見られる表情であろう。”という文章にまえがきは始まっている。いつものくせで、まえがきの次にあとがきを見る。あとがきは、“この機会を用意してくださった中央公論社の方々に、とくに野中正孝氏に謝辞を捧げるものです。”と終わっている。とにかく私は『胎児の世界』を購入して、新幹線の中でそれをじっくり読んだ。
読み終わった私はこのユニークな著者に会いたくなり、面会を申し出るまえに、著者から謝辞を呈されている編集者の野中正孝さんに会って、三木先生についての情報をまずもらおうと心に決めた。「元の理」の学際的展開を追求している私の目指すところは、著者に「元の理」を「胎児の世界」から解釈してもらおうという点にしぼられている。「元の理」とは別名「泥海こふき」ともいわれるが、天理教祖中山みきが啓示した壮大な人間創造と救済の説話であり、コスモロジーである。東京駅に着きさっそく中央公論社に電話したが、野中さんは『胎児の世界』の編集を最後に退職したとの事。落胆した私は所用のある赤坂のアジア会館におもむいた。オセアニア研究所の小林泉君との約束があったからである。小林君は十五年ほど前、私が天理教シンガポール出張所長の頃、南洋大学に留学生として来ていた頃からの知己であり、帰国後しばらくして、日本シンガポール協会の事務局長をもつとめていたことがある。シンクロニシティーとはこのことをいうのだろうか。『胎児の世界』をついさきほど読んだことを少しも知らない小林君が私に、「実は井上さん、野中正孝という人物があなたに会いたがっている」という。もちろん私は、『胎児の世界』の著者である三木先生はもとより編集者の野中正孝さんとも一面識もない。小林君の話を聞くと、中央公論社を退社した野中さんを小林君がスカウトしてきて、日本シンガポール協会の事務局長になってもらったというのである。私は同協会発足当初からその活動に関わっていたこともあって、新任の野中さんは協会の過去の記録を読み込んでいくうちに、私のことを知るに及んで是非私に会ってじかにシンガポールのことについて聞きたいという想いをもっているとのことであった。是非私も会わせてもらいたいというと、二、三分も経たないうちに野中さんがやってきた。シンガポール協会もオセアニア研究所と同じビルの中にあるから、野中さんがすぐ現われるのは何の不思議もない。しかし、三木先生に会いたいという私の希望は、またしてもこわれてしまった。野中さんは、三木先生は生まれてから伊豆の大島に一回行っただけで、東京より外に出たことはないし、また出ようともしない、一風変わった学者で、まあ私があなたのご希望を伝えても、ご希望を叶えるのは難しいでしょうとの事であった。
何かいい智恵はないものかと考えていると、『胎児の世界』の中の一文が想い出されてきた。それは胎児の“上陸の形象”について、先生が鶏胚の上陸の発見をされたときのことを、最も感動的に語られている文章で、かの有名なケンブリッジ大学の生化学者であったジョゼフ・ニーダムについて述べておられるところである。
私はちょうどその頃、天理国際シンポジウム86「コスモス・生命・宗教」の開催に向けて、何をかくそうジョゼフ・ニーダム先生を招請するため、文通を続けていたのであった。東京の天理国際シンポジウム事務局で、その頃働いていた私の教え子でもあった飯富幸枝さんが、これまた偶然に東京芸大の出身で三木先生は恩師の一人であるという。そこで彼女にニーダム先生の話を糸口として、「元の理」を先生に読んでもらう事を依頼したのである。芸大の大学院で「能」を専攻していたというこの教え子の紹介で、はじめて「元の理」を読まれた先生は、とにかくその内容に驚かれたらしい。さっそく天理での講演を快諾下され、その時の講演が縁となって、哲学者の市川浩先生との対談が成立した。聞くところによると、他の東京の出版社がこの二人の先生を会わせようとして、対談のチャンスをねらっていたらしい。
何事にも慎重な先生は、講演では、十分にまだ研究していないので「元の理」についてはふれないとの予定であったが、本筋の話に必要な胎児のスライドが講演の途中、機械の故障で動かなくなった。機械を修理している時間を利用して、「元の理」について私が先生の感想を求めたのであった。昨晩は井上さんに「元の理」について数時間私から感想を聞き出されて、いささかまいっているのですが、と前置きして語られた先生のユニークな「元の理」の印象に、天理の聴衆は大きな驚きと感動でもって反応した。いま考えるとスライド映写器の故障は、先生に「元の理」について語らせるための神のいたずらであったのかも知れないと思う。
講演ののち、山の辺の道を独りで歩きたいと言われ、翌朝リュックを背負って石上神宮の参道から森の中に独りすい込まれるように消えてゆかれた。山の辺の道は十七、八年前子供と歩く予定であったが、出発のその朝、子供の発熱で取り止めざるを得なかったのがようやくいまになって実現したとの事。あとで聞くと、途中、山の辺の道から西に出て三昧田という村にある天理教祖のご誕生殿を訪れ、人間宿し込みの場所と教えられるぢば・天理の神殿を真北に見て、胎内を想起させるようなこの大和盆地の一角の高台から、しばし瞑想にふけられたとのことであった。
後日、先生にいただいた胎児の聞く胎児音のテープのコピーを、天理国際シンポジウムに出席された哲学者である中村雄二郎先生に差し上げた。季刊『ヘルメス』第十号に掲載された「六大にみな響きあり――宇宙リズムと形態生成」の中で、宇宙の音と対照して展開された雄大なコスモロジーの世界は、「胎児の世界」がみごとに「宇宙の世界」とすぐれた哲学者によってドッキングされた論文となっていた。
一九八六年十二月十八日、天理国際シンポジウム東京会議が終了した翌日、私は三木先生に連絡をとり、赤坂プリンスホテルでジョゼフ・ニーダム先生、魯桂珍先生と昼食をともにとっていただいた。“『胎児の世界』は、ニーダム先生一人に捧げるために書いたようなものです”と私にかつて申されていた三木先生は、いささか生化学者として大先輩の八十四歳の老碩学を前にして緊張しておられるように見うけられた。
二、三英語の論文をニーダム先生に見せられ、ニーダム先生の胎内学のいまや古典的名著となっているといわれる著書にサインを求められ、ニーダム先生が道教に興味をもたれたのは、先生の発生学の諸研究にその動機があったのかなどと、さかんにその因果関係を尋ねておられたが、ニーダム先生の返答は否であった。
あとで魯先生に聞いたのだが、ニーダム先生が道教や中国文明について興味をいだかれるようになった遠因、つまり魯先生との偶然の出会いは、突然降り始めた雨であった。中国から留学して間もない魯先生は、ケンブリッジ大学構内で講義が校舎がどこか分からず、雨をさけてビルの軒下で途方にくれておられた。その時、向こうから雨の降る中を自転車でこちらに向かって来られたのが若き頃のニーダム先生で、ニーダム先生が親切に目的地の校舎にまで案内して下さったとの事であった。あの時、雨が降り出さなかったら二人の出会いはなかったろうとの回想であった。
いずれにしても、人生における不思議な人と人との出会いは、人間には偶然とも思えるが、天の深い支配によるものではないかと感嘆せざるを得ない。
(天理教本部准員・天理やまと文化会議事務局長)
(この拙文は、天理やまと文化会議編『G−TEN』第二十二号特集・「生命の記憶」のまえがき“回顧”に記したものに加筆訂正したものです。)