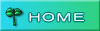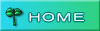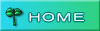81. 人は人を恋の姿や花に鳥
今泉準一
三木さんとの出会いは富永先生の会である。記憶は定かではないが、浦和での毎週土曜日の会で、お会いし、何年か経つうちに顔と名前を自然と覚え、帰路、偶然電車で席を隣り合わせて二言・三言会話を交わすと言った間柄となった。ただ、その間のある日、私は腰を抜かさんばかりに、というとすこし大げさないい方と言われるかも知れないが、実感としてはそのような感じで、三木さんのことばに驚いたことがある。そのときから、この人はこんな風に其角を読む人か、またこんな読み方もあるのか、と深く教えられたのである。
これより前、たしか昭和三十三年のことであったと思う。私の、メモが間違っていないとすれば十二月二十一日とある。浦和での土曜日の会で、前段と後段とに分けて前段であったと思う、其角を読むということになった。そのとき、国語の教師であり、俳句が好きであったというだけの理由からであろう、千谷氏から素稿を書くように言われ、氏を通じて富永先生に見ていただいたところ、これでよい、これでやろう、とおっしゃったとかで、詫摩さんがガリ版に刷り、皆に配布、これを通して富永先生のお話を伺い、また皆さんの感想を聞く。そんな風な会になった。
わからぬままに、年代順に作品を並べ、それまで富永先生からお教えいただいた其角に関する知識を基に、いわば受け売り式に書き、またお教えをうけていない作品などは私なりに勝手に書いただけのものだった。この会は大変私の勉強になった。富永先生のお話をいかに私が自分勝手に解釈していたかを随所で知り得たこと、と同時に皆様の発言で私には思いも寄らなかった解釈を教えられたからである。前に、腰を抜かさんばかり、と書いたのはこの後者の中の一つである。しかもこれは帰りの電車の中であった。
表題に「人は人を恋の姿や花に鳥」と書いたのは、この句の三木さんの解釈を聞いてびっくりしたことをいまも鮮明に思いだすからである。この句を浦和の土曜日での会で読んだのは、これもメモによれば昭和三十五年七月十六日とある。よく帰りの電車の中ではその日に読んだ句が話題になる。しかしその日でなかったことは覚えているのでこれから後のことであったろう。とにかく其角について漫然と話題にしていたときのことである。多分三木さんがもう四十歳前後になられたころのことであったと思う。
三木さんは「かまきりの尋常に死ぬ枯野かな」の句がいかにかまきりをよく見ているかを口にしておられたが、これは私もかまきりの生態を常識的な意味で知っており、句がおのずからにこの意味を込めて味わうに足るものをもっているから、科学者でもある三木さんが感心するのももっとものことだなと思いつつ聞いていたが、同時に上述の「人は人を」の句を口にされるので、私にはなぜこの句をそれほどに感心なされるのかがわからず、どういうところが面白いのですか、と尋ねた。私の聞き違えがあるかも知れないが、私が理解し得た答えはつぎのようなものであった。
顕花植物・鳥類の発生の後、人類は発生する、この句はこの人類の姿がおのずからに詠めている。これには驚いた。すでに私は千谷氏からクラーゲスを教わっていて、私なりに、文字発生以前の人類に眼を向けなければ人間はわからない、このことは痛感していた。「人は人を恋の姿や」までは私も人間本然の姿が詠めていると同時にそれはそのままおのずからに人類史にまで眼が届いている句だとは思っていた。しかし「花に鳥」にそこまでのこの句のもつ詩眼を詠みとってはいなかった。このときの驚きは大変なものであった。
その後、三木さんの論文や御著書を読み、これが科学的な裏づけをもって堂々たる、あるいは壮大の語がふさわしいか、三木理論となって展開されて行くのを知り、前の驚きが心の中での拍手といおうか、あるいは名選手の活躍に遠くから旗を振っての声援といおうか、そんな気持ちで見守る日々となった。
富永先生がなくなられてから、あまりお会いする機がなく、何かの行事などで顔を合わせるだけのつきあいとなったが、いまから数えると六年前、限定五百ページほどの一書を書き、三木さんにさし上げたことがある。その翌年の年賀状に読後感が余白に簡潔に書かれてあった。あんな大部のものを読んでいただいたことに感謝するとともに簡潔な文の中に籠る情熱に深い親愛感とその健在に大きな期待感をもったことも鮮明な記憶となってよみがえる。遠くて案外に近かったおつきあいとも言える。うわさはいつも耳にしていた。偶然のことだが、私の姪が芸大生となって、学内でも最も学生を惹きつける講義は三木先生の御講義だ、と語っているのを聞き、内心、当然のことだ、と思ったりしたのもその一つである。
三木さんの訃報は私にとって二度目の、これはまったく質を異にした驚きであったが、一方では「やっぱり」という感じがした。というのは三木さんのひたむきな探求はひたむきのゆえに私はその健康に不安を感じていたからである。ただ私は三木さんをわれわれとは資質を異にした天成に恵まれた人なのだと考えていたので一方でそんな不安は凡夫の取り越し苦労だ、とうかつにも思ってもいた。それだけに痛魂に耐えない。
(国文学・明治大学)