ゲーテの『自然』について
ゲーテ Johann Wolfgang von Goethe 1749〜1832
(詩人・劇作家・小説家・科学者・政治家)
★ 下線はすべて引用者
「ゲーテにとって自然とは何であったか」、というテーマは恐ろしく大きなテーマでして、「ゲーテとはどういう人間であったか」というテーマにほぼ等しいと言えるかもしれません。それほどゲーテにとって「自然」が持つ意味は大きかった訳です。もちろんゲーテにとっての自然とは、「自然」科学という場合のような狭い意味での自然ではなく、「世界あるいは宇宙全体をこのようにあらしめている働き」というほどの広い意味でして、その力は当然歴史の中にも、われわれ個人の心にも働きかけてくるものです。ゲーテがスピノザの汎神論の影響を強く受けていることは広く知られていますが、ゲーテにとって自然とは、「神」という概念にほぼ等しかったと言えるかと思います。彼はある詩の中で次のように歌っています。
世界をその内奥において動かし、
みずからの中に自然を、自然の中にみずからを包蔵することこそ、
神にふさわしい。
こうして、神の中に生き動き存在するものは、
神の力と霊とにみたされぬということはない。
Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen,
So daß, was in Ihm lebt und webt und ist,
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.
(Hamb. Ausg. 1., S. 357)
ところで、ここに出てきた「神の中に生き、動き、存在する」という言葉は、ギリシアの詩人の詩の一節だそうですが、新約聖書・使徒行伝の中でパウロが使ったことで有名です。ゲーテはこの言葉が大変気に入っていたようで、ここだけでなく、詩や談話の中などで繰り返し繰り返し使っております。これは恐らくゲーテが一番多く引用した言葉だろうと思われます。
ゲーテにとっては、「神=自然」の中に「生き、動き、存在する」ことがすべてであったと言っても過言ではないでしょう。生涯、ゲーテを敬愛して止まなかったアルベルト・シュヴァイツァーは、ゲーテの使命とは、「深く深く自然と結びつきながら、自分自身を、この上もなくゆたかで高貴な自然の一片として、われわれにつたえるということにあった」(シュヴァイツァー著作集第六巻 S.49)と言っております。このことは思想的な点に関して言えるだけではなくて、ゲーテという人間そのものが自然そのもののような存在だったということです。ゲーテを評してある友人が次のように言っています。「ゲーテはものに憑かれたような人で、ほとんどいかなる場合にも自分の意のままに行動することが許されていないようだ。・・・樹木の花がほころび、種が熟し、木が高く伸びて樹冠を作っていく」ように、ゲーテという存在もそのように自然の法則に縛られていた、あるいは彼自身が自然そのものであった、というのです。
「自然」を切り刻んでいくようなニュートンの機械論的姿勢に対して、ゲーテは「愛によってのみ、人は自然に近づく」と言っていますがそのような自然に対する畏敬に満ちた態度は、このゲーテの自然観と切り離すことのできない関係にあることは申すまでもないことです。
ところで、ゲーテは自分の作品をすべて、「告白」だと考えていました。「詩はすべて機会の詩(Gelegenheitsgedichtある出来事をキッカケとして生まれる詩)でなければならない。つまり、現実が詩作のための動機と素材をあたえるのでなければならない」(「ゲーテとの対話」)と彼は言っていますが、そういう意味でも、彼の「生涯」と彼の「作品」を分けて考えることはできないでしょう。それで今日は、「ゲーテの自然」について考えるにあたって、年譜にそって彼の生のあり方と、その時期の彼の作品の言葉を、併せて考えていきたいと思っております。彼の自然に対する態度は生涯あまり変わらなかったので、繰り返し同じことを述べることになるかもしれませんが。
1749年
 8月28日、マイン河畔のフランクフルト市(当時人口三万、重要な商業中心地)に生まれる。父が帝室顧問官の称号をもつ裕福な家。母方の祖父はフランクフルト市長。
8月28日、マイン河畔のフランクフルト市(当時人口三万、重要な商業中心地)に生まれる。父が帝室顧問官の称号をもつ裕福な家。母方の祖父はフランクフルト市長。
すなわちゲーテは「良家のお坊ちゃん」としてこの世に生を受けたわけでして、またその後も宮廷に仕え貴族に近い生活を送っております。ですからゲーテ文学は、革命のような社会変革の時代や、プロレタリア文学の時代には、「王侯の下僕」の文学として無視されていたこともあるのです。庶民の生きる苦しみの何一つ知らない人間が、本当の人間性の深みにまで達することができようか、という疑問が突きつけられていたのだと思います。しかし、強制収容所で地獄を味わったあのフランクルのような人が、ゲーテの言葉を支えとしていたという事実は、ゲーテの文学にはそのような批判を跳ね返すだけの強靱なものが存在するのだと言えそうな気がします。
フランクル『それでも人生にイエスと言う』より
ですから、私たちは、どんな場合でも、自分の身に起こる運命を自分なりに形成することができます。「なにかを行うこと、なにかに耐えることのどちらかで高められないような事態はない」とゲーテはいっています。それが可能なら運命を変える、それが不可避なら進んで運命を引き受ける、そのどちらかなのです。
1759年(10歳)
ゲーテの語学的、文学的才能はすでに驚異的なものとなって現われている。
1765年(16歳)
法律を学ぶためライプツィヒ大学に入学。精神の自由を求め奔放な生活に傾く。
ライプツィヒは当時「小パリ」と言われ、当時世界の文化的中心であったパリの影響を色濃く受けていました。そのフランス文化の中心に啓蒙主義があったことは、後でも述べることになりますが、極めて重要なポイントです。
1768年(19歳)
二年前に知り合い、恋愛関係にあったケートヒェンと訣別。肺結核の闘病のためフランクフルトの生家に帰る。クレッテンベルク嬢を知り宗教的感化を受ける。
ライプツィヒ大学時代の放蕩生活で、ゲーテは生死の間を彷徨うほどの大病を経験して、まさに九死に一生を得ました。それまである意味で軽薄な生き方をしていたゲーテの生が、「死」と直面することで、グッと深まったと言えます。クレッテンベルク嬢というのは、ゲーテの母親の友人で、ヘルンフート派の修道女でした。ゲーテは、キリスト教会には反感を持ち続けましたが、真のキリスト教に対しては、生涯変わることなく敬意を払っておりました。「太陽とイエス・キリストの前では自分は無条件にひれ伏す」とまで言っています。ところでゲーテの言う「真のキリスト教」とは、正統的キリスト教の立場からすると、しばしば異端的であると見られていることも知っておく必要があろうかと思います。それはゲーテの宗教が自然宗教であって、啓示宗教ではないからです。啓示宗教と言えば、カルヴァンやカール・バルトなどがその代表でしょうが、そのバルトが、自然宗教の代表として挙げていたのがゲーテでした。事実ゲーテは、キリスト教の裏の歴史に連綿と流れてきた、キリスト教神秘主義の影響下にありました。正統的キリスト教が原罪を説き、キリストによる贖罪・救済を説くのに対して、神秘主義=自然宗教は原罪を否定し、救済者キリストを介さず、神との直接体験、神秘的合一(unio mystica)を重視します。ゲーテの自然宗教が具体的にどのようなものであったか、―それはこのクレッテンベルクをモデルにした物語『美しき魂の告白』の中で、主人公に言わせている次の言葉が言い尽くしていると思います。「わたしはほとんど命令とか掟とかいったものを意識したことがありません。わたしを導き、つねに正道をたどらせてくれるもの、それはひとつの衝動です。心の欲するままに勝手にふるまいながら、それでいて何の悔いもおぼえなければ、咎めだてされることもないのです。」 (『美しき魂の告白』より)
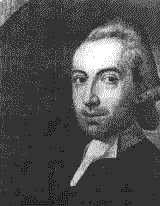 1770年(21歳)
1770年(21歳)
4月、シュトラースブルク大学に入学。ヘルダーを知り、やがて大きな影響を受ける。ゼーゼンハイムの牧師の娘フリデリーケと交わり愛情を抱く。
先ほども申しましたように、ゲーテがライプツィヒで影響を受けたフランス文化─それが当時のヨーロッパ文化の主流だったと言っていいでしょうが─その中心に、啓蒙主義・合理主義・理性中心主義がありました。ゲーテはこれに真っ向から反逆することになるわけですが、そのキッカケとなったのが、シュトラースブルク時代です。この時代に3つの重要な出会いがありました。1.ヘルダー、2.フリデリーケ、3.自然です。ヘルダーはゲーテよりわずか5歳だけ年上の思想家で、ゲーテと出会った当時まだ26歳でしたが、すでに文芸批評家として名をなしていました。「ゲーテがヘルダーから学んだものは、一言で言えば、「自然」に根ざすものだけが真実であるということ、すなわち文学に関して言うならば、理知や技巧による「芸術詩」(Kunstpoesie)ではなく、シェークスピア、ホメロス、オシアン、旧約聖書、民話などの自然を養いの土壌とする「自然詩」(Naturpoesie)のみが真である」(芦津丈夫:『ゲーテの自然体験』より)ということでした。民族の魂に根ざした文学、理性ではなく感情に根ざした文学を説くことによって、ヘルダーはゲーテを通して、シユトゥルム・ウント・ドラング(疾風怒濤)の思想的指導者となっていきます。
1771年(22歳)
 抒情詩の秀作「五月のうた」、「野ばら」などが生まれる。
抒情詩の秀作「五月のうた」、「野ばら」などが生まれる。
先ほど、この時代に3つの重要な出会いとして、ヘルダー以外にフリデリーケと、「自然」をあげました。両者、つまりフリデリーケと自然を、二つに分けて考えることはできないでしょう。フリデリーケとは友人の紹介で知り合ったのですが、彼女はゼーゼンハイムという小さな村の牧師の娘でした。シュトラスブルクからそこまでは馬で約1時間の距離でしたから、ゲーテは自然の中を馬に乗って通った訳です。生まれ故郷フランクフルトやライプツィヒの周辺に自然が無かった訳ではないでしょうが、今や自然そのもののような素朴な村娘フリデリーケに会うために、彼は恐らく、太陽の光を浴び、新鮮な空気を吸い、鳥の声を聞きながら、足繁くフリデリーケのもとに通ったことでしょう。この時期、数多くの恋の喜びと自然の恵を歌った抒情詩が生まれます。この時期のゲーテの詩を「ゼーゼンハイムの詩群」と言いまして、真のドイツ文学はここから始まった、というドイツ文学史家もいるくらい、生き生きとした自然感情に満ちた重要な詩が多く生まれています。そのうちの一つがシューベルトなどの作曲で有名な「野ばら」です。
Heidenröslein 野ばら
Sah ein Knab' ein Röslein steh'n, 子供が ばらを
Röslein auf der Heiden, 野ばらを見た
war so jung und morgenschön, みずみずしさに
lief er schnell es nah' zu seh'n, すぐ駆けよって
sah's mit vielen Freuden. うっとり ながめた
Röslein, Röslein, Röslein rot, ばら ばら 紅ばら
Röslein auf der Heiden. 野に咲くばら
Knabe sprach: Ich breche dich, 子供が「ばらよ
Röslein auf der Heiden, 折るぞ」といった
Röslein sprach: Ich steche dich, ばらがいうには
Daß du ewig denkst an mich, 「記念に刺すわ
Und ich will's nicht leiden. だまってませんよ」
Röslein, Röslein, Röslein rot, ばら ばら 紅ばら
Röslein auf der Heiden. 野に咲くばら
Und der wilde Knabe brach 子供は かまわず
's Röslein auf der Heiden; 野ばらを折った
Röslein wehrte sich und stach, ばらは さからい
Half ihm doch kein Weh und Ach, 刺したけれども
Mußt' es eben leiden. ただ泣くばかり
Röslein, Röslein, Röslein rot, ばら ばら 紅ばら
Röslein auf der Heiden. 野に咲くばら
訳: 井上正蔵
この一見美しく無邪気な抒情詩の裏には、実は恐ろしい力が働いていたのです。下線部に注目してください。子供をゲーテと、そしてバラをフリデリーケと読みかえてみたらどうでしょう。ゲーテはみずみずしいバラを手折ります。すなわち、フリデリーケに一言の別れの言葉を告げることもなくシュトラスブルクをあとにして、フランクフルトに帰ってしまいます。フリデリーケは悲しみのあまり、病の床に着き、一時は命まで危ぶまれるほどの大病を病み、生涯を独身で通しました。一方のゲーテはと言えば、このあと彼は何人の女性たちに囲まれることになることでしょう。なぜ彼がフリデリーケを捨てたのか、それはドイツ文学史上、謎とされています。この件については、後ほど再び触れることになります。
1772年(23歳)
5月、法律実習のためにウエッツラルヘ。『若きヴェルテルの悩み』の女主人公のモデルとなるシャルロッテを知り、愛する。
『若きヴェルテルの悩み』はゲーテの作品で一番読まれたもので、この席におられる方の中にも読まれた方はキット多いと思います。この作品からも、ゲーテの自然観を非常にハッキリと感じとることができます。
『ヴェルテル』の眼にうつった自然

ぼくは、たぎり落ちる渓流のほとりの丈高い草のなかに臥し、大地に身をよせて数多くの小さな草たちのさまざまな格好を見つめたり、立ちならぶ茎と茎とのあいだにはさまれた小世界のうごめきや、小さな虫や蚊たちの数限りない、見きわめもつかぬ姿をひとしお胸の間近に感じる。また、
みずからの姿に似せてぼくたちを造ってくれた全能者の現存、ぼくたちを永遠の歓喜のなかに漂わせ生かしておいてくれる全愛者の息吹、ぼくはそれをひしひしと感じる。 (5月10日)
自然の一切のなかにひそんでいる破壊の力、これがぼくの胸を掘りくり返すのだ。この力がつくり出すものは、すべて自分をも隣人をも破壊してやまない。これをおもうと、ぼくは不安におびえ、よろめく。ぼくの周囲には、天があり、地があり、それらの織りなす力がある。しかし、ぼくの眼には、永遠に呑みつくし、永遠に反芻する怪物の姿しかうつらないのだ。 (8月18日)
訳: 前田敬作
下線部に注目してください。ここで強調しておきたいのは、「一切を愛で包み育む創造的自然」と「一切を破壊してやまない怪物的自然」の共存です。しかも、ゲーテにおいて特徴的なのは、宇宙そのもののように、両者がどちらに偏るということなく共存している点です。この点がゲーテの自然を理解するうえで、非常に重要な、あるいは最も重要な点ではないかと私は思っております。この点に関しては後に再び触れることになります。
1774年(25歳)
『若きヴェルテルの悩み』を短期間で完成、発表してセンセーションをまき起こし、『ゲッツ』の成功とともに、いまやシユトゥルム・ウント・ドラングの輝かしい旗手となると共に、ヨーロッパ的名声を得るにいたる。
1775年(26歳)
銀行家の娘リリーを知り愛し合い婚約までするが、訣別。「湖上にて」その他の名詩が作られる。11月、招かれてワイマルへ行き、定住。
『湖上にて』(初稿)
Ich saug' an meiner Nabelschnur われは臍の緒にて
Nun Nahrung aus der Welt. 世界より養分を吸う。
Und herrlich rings ist die Natur, われを胸に抱く
Die mich am Busen hält. 四囲(しい)の自然の輝かしさよ。
Die Welle wieget unsern Kahn 波はわれらの小舟を
Im Rudertakt hinauf, 櫂の拍子に合わせてゆさぶり、
Und Berge Wolken angetan 雲をまとう山々は
Entgegnen unserm Lauf. 行く手にわれらを迎える。
訳: 芦津丈夫
この詩に出てきた「臍の緒」という言葉は、自然哲学者・三木成夫の著書『胎児の世界』を思い起こさせます。この『胎児の世界』の192ページを見ますと、「今日、地球上に生息するすべての生きものは、こうして、その出生の遠近を問わず、ことごとく原初の生命球を介して宇宙と臍の緒で繋がることとなる。したがって、その生の波は、どの一つをとっても、宇宙リズムのどれかと交流する」云々と書かれています。
まさにこの詩において、母なる自然に溶け込んで、「宇宙と臍の緒で繋が」り、「自分自身を自然の一片」と化してしまったゲーテの姿を見ることができのではないでしょうか。
この詩が成立したのは、彼が婚約していた、フランクフルトでも有数の資産家の娘リリー・シェーネマンと、決別する前後だとされております。彼女は美しく、気品に満ち、気だての優しい娘だったようです。そんなリリーと婚約解消に至ってしまった経緯としては、家柄や家風の違いなども背景にあったようですが、フリデリーケの場合もそうであったように、何かあるデモーニッシュな存在に牽かれて逃げ出したようなところがあります。ゲーテが女性から逃げ出したのは、これが初めてではありません。また、この後にも何度も同じようなことが繰り返されるのです。恐らく、女性の中に、自らを高め浄めるものを感じ、そこに恐らく唯一の生の燃焼を覚えながら、同時にそこに自らの自然を束縛するものをも感じ取っていたからではないかと思われます。どのような女性関係の場合にも、シラーとの奇蹟のような友情の場合でさえも、彼は自分の或る部分を与えきらずに保留したようです。ゲーテがまったく身を委ねることができたのは、自然にたいしてだけでした。この場合も女性から遠ざかり、逃げていく先は自然だった訳です。
ここでゲーテの女性との関係についてもっと詳しく話すべきかもしれませんが、それはもう少しあとにまわしましょう。それも重要なことです。何故なら、これもゲーテの中の自然の然らしめるところと考えられますから。
 1776年(27歳)
1776年(27歳)
政治生活に入る。シュタイン夫人への愛、たかまる。六月枢密会議(閣議)に出席。また鉱山監督の任に当る。
『旅人の夜の歌』を読んでみましょう。
Wandrers Nachtlied 旅人の夜の歌
Über allen Gipfeln 見はるかす
Ist Ruh'; 山々の頂
In allen Wipfeln 梢には
Spürest du 風も
Kaum einen Hauch; 動かず
Die Vögelein schweigen im Walde. 鳥も鳴かず
Warte nur, balde まてしばしやがて
Ruhest du auch. 汝も休はん
訳: 西田幾太郎
Emil Staigerという批評家などはヨーロッパ抒情詩の中でこれが最も優れていると言い切っています。ゲーテ自身とても気に入っていた詩です。ただ美しいだけの何気ない短い詩のように思われますが、意味しているところは重たく深いとされています。ゲーテは21歳でヘルダーと出会い、感情を爆発させたような作品『ヴェルテル』などを書き、シユトゥルム・ウント・ドラングの旗手(きしゅ)となる訳ですが、それはあまりに激しい文学運動でした。この文学運動の担い手であったほとんどの若い文学者たちが、ゲーテとシラーを除いて、自殺し、発狂したと言われています。二人が生き延びたのは、その器の大きさと、精神の強靱さ故だったと思われます。
そんなゲーテにとって、シュタイン夫人との出会いは大変大きな意味を持っています。彼女は、崇高で高貴な女性として描かれた『イフィゲーニエ』のモデルであると言われていますが、ゲーテにとってギリシア的調和を一身に体現した女性と映った訳です。そんなシュタイン夫人との出会いによって、激しい感情は沈静化してゆきます。この詩はそんなある日(31歳)、キッケルハーンという山に登ったときにできた詩です。ゲーテにとって、シユトゥルム・ウント・ドラングの時代はここで終わり、古典主義の時代がここから始まります。
ついでながら、ゲーテはこの時期、仕事上の必要から鉱物学の研究に従事しています。
1782年(33歳)
大蔵長官となり、実質的には宰相として政治に専心。
1784年(35歳)
人間の顎間骨を発見。期せずして進化論の道をひらく。
1786年(37歳)
多年尽力した政治への献身も理想通りにいかず行きづまり、シュタイン夫人との稀有の愛情も堪えがたくなる。誰にも告げずイタリアへ旅立つ。
 1788年(39歳)
1788年(39歳)
ローマを去り、六月、ワイマルに帰る。イタリア滞在により古典主義の明晰な芸術観を体得。シュトュルム・ウント・ドラングの精神克服され新しく『ファウスト』の構想が成る。ワイマルでは、実質上の政治的公職から解放される。造花工場の女工クリスティアーネ・ヴルピウスを知り、愛して家に迎え入れる。
1789年(40歳)
7月、フランス革命が起こる。ゲーテはフランス革命の精神には共感を覚えても、現実にあらわれる粗暴な大衆の暴力には共鳴できず、これに反撥。
1790年(41歳)
『植物変態論』完成。芸術よりもむしろ自然研究に執心(しゅうしん)。光学に惹かれ、ニュートン説の誤りを確信。また『動物の形態試論』に着手。
1794年(45歳)
イェーナに植物学研究所が設立され、ゲーテがこれを監督する。シラーと出会い、友情が急速に深まる。
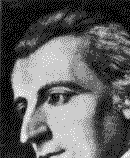 1796年(47歳)
1796年(47歳)
シラーと文学上の提携をする。二人の協力により、ドイツ古典文学の隆昌(りゅうしょう)を見る。
『箴言と省察』より
古典的なものをわたしは健全なものと呼び、ロマン的なものを病的なものと呼ぶ。
Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke.
ゲーテはドイツ文学では、「ゲーテ時代」という時代に入れられていますが、外国、例えば英米の文学史では、ゲーテはロマン主義者として数えられているとのことです。ところがゲーテ自身はロマン主義に対して、必ずしも好意的ではありませんでした。これについては後でベートーヴェンとの出会いのところで詳しく述べたいと思っています。
1805年(56歳)
5月、親友シラーが逝去し、ゲーテは悲嘆にひたる。
1806年(57歳)
『ファウスト』第一部完成。神聖ローマ帝国滅亡。ナポレオンがワイマルに入る。10月、クリスティアーネと正式に結婚式を挙げる。
1808年(59歳)
10月、エアフルトでナポレオンと対面。ナポレオンが『若きヴェルテルの悩み』を戦陣にまで持参してきていたこと、七回も読んだということに感銘。更にワイマルでも再会し、ナポレオンからレジオン・ド・ヌール勲章を授かる。
1810年(61歳)
10年以上断続的に研究していた『色彩論』第一巻を刊行。
1812年(63歳)
7月、ベートーヴェンに会う。だが二人は理解し合えなかった。
ブレンターノというロマン派の詩人がいますが、その妹はベッティーナといってドイツ文学史の中で、感情の起伏が異様に激しい女性として知られています。彼女はゲーテとベートーヴェンの熱狂的な崇拝者で、何とか両者を近づけたいと色々画策し、やがてある湯治場(とうじば)で二人を会わせることに成功します。二人は、最初からあまりかみ合わないのですが、特にゲーテにとってしっくりこなかったようです。そして、ある小さな事件が二人の仲を決定づけます。二人が散歩していたとき、数人の貴族と狭い道ですれ違うことになりました。野人であるベートーヴェンは、あんな連中に道を譲ったりする必要はない、とどんどん進んでいこうとします。一方宮廷人であるゲーテはと言えば、道の脇に避けて、貴族たちに道を譲り丁重に頭を下げました。その後二人は二度と会うことはなかったようです。
二人の関係に関しては、一般には、ゲーテにベートーヴェンの音楽を理解する能力が欠けていた、と言われています。ツェルターという二流もしくは三流の音楽家を重んじていたことなどから、音楽そのものを理解する能力がゲーテには欠けていた、という風にさえ言われることがあります。ロマン・ロランは、しかし、それは逆だ、と言います。ゲーテほどベートーヴェンの本当の恐ろしさを、あるいは音楽そのもの、ロマン的のもの、ディオニュソス的なもの、の恐ろしさを本当に理解していた人間はまれである、とロラン言います。(参考資料の3-1:
http://www.geocities.jp/seto_no_shorai/3_gakushukai_handout.htm)
ベートーヴェンは、言うまでもなくドイツ音楽ロマン派の巨匠です。ロマン主義あるいはロマン派とは一体何でしょうか?トマス・マンはこれを、これ以上的確に表現できないほど巧く表現しています。彼は言います。
「ドイツ・ロマン派、それはあの最も美しいドイツ人の特性、ドイツ人の内面性の発露以外の何物でしょうか。多くの憧憬に満ちた夢想的なもの、幻想的で妖気を漂わせたもの、深遠で風変わりなもの、それにまた高度な芸術的洗練、あらゆるものを超えて漂う反語精神(イロニー)、こうしたものがロマン派の概念と結び付いております。しかし、ドイツ・ロマン派について語るとき、私が考えているのは、実はこのことではありません。それはむしろ、ある種の暗い力強さと敬虔さなのです。あるいは、こう言ってもいいかもしれません。それは自分自身が、地底の世界に通じるような非合理で悪霊的(デモーニッシュ)な生命力に近いところに、すなわち人間の生命の本来の源泉の近くにいると感じており、他方単に理性的でしかない世界観や世界論に対しては、自分はもっと深い理解を持ち、聖なるものともっと深い結びつきを持っているとして反逆する、そのような魂の古代性なのです」。
これはシュトゥルム・ウント・ドラング時代のゲーテにそのまま当てはまる言葉ではないでしょうか?すなわちシュトゥルム・ウント・ドラングとは広い意味でのロマン主義であって、「ロマン的なもの」が「病的」であることを一番肌で感じていたのはゲーテ自身だったのではないでしょうか。だからこそ彼は、シユトゥルム・ウント・ドラングを生き延びることができ、古典主義に移行できたのではないでしょうか。そして「おのれの内面に、実に完全な、調和的(?)宇宙を造りあげ」たのではないでしょうか。
私見を述べることが許されるならば、ゲーテの内部では、「一切を愛で包み育む創造的自然」と「一切を破壊してやまない怪物的自然」が実は「調和」することなく、共存していたのではないか。つまり、ゲーテにおいては、「一切を愛で包み育む創造的自然」は同時にまた「一切を破壊してやまない怪物的自然」でもある。両者が調和しないままに共に肯定されている。あるいはこう言うことができるかもしれません。両者が両極をなして、波のように押し寄せて来るのである、と。
今、分かり易くするため、試みに図式化して考えてみますと、以下のようになろうかと思います。
ゲーテの場合の場合は、一切を愛で包み育む創造的自然(ギリシア的、古典的、アポロン的、「光」)と一切を破壊してやまない怪物的自然(ドイツ的、ロマン的、ディオニュソス的、「闇」)がどちらに傾くということもなく共存している。
これに対してベートーヴェンの場合は(そして恐らくルターやニーチェの場合も)、一切を破壊してやまない怪物的自然 (ドイツ的、ロマン的、ディオニュソス的、「闇」)にずっと比重がかかっている。
この極性が『胎児の世界』で言われる「食の相」「性の相」とどのように関係しているかは私には全く分からないのですが、後で話しあうテーマの一つとしてもいいのではないかとも思っております。
さて、ゲーテのこの恐ろしいまでの「自然肯定」についてもう少し触れてみましょう。正確な言葉は忘れたのですが、彼はどこかで確かこんなことを言っていました。「世の中の人々は、革命や動乱や戦争など、歴史の荒波のなかで右往左往しているが、自分は断崖の上に立って、平然と岸で座礁した船を見下ろすように歴史を見つめている」と。実際ゲーテは43歳と44歳のときに、二度ほど出征していますが、陣営で彼は光の研究に没頭していた、と言われています。周りで人が殺されていく戦場で、光の研究に勤しむ政治家とは一体何者なのでしょうか。私は、そんなゲーテの姿に、強制収容所で「世界ってどうしてこう奇麗なんだろう」という言葉を漏らしたあのユダヤ人を重ね合わせたい気がします。あるいは、『災難に逢ふ時節には災難に逢ふがよく候』と言った良寛和尚の言葉を思い浮かべます。
そして、このように肯定された世界の全体は、ゲーテの場合、最終的に「闇」にではなく、「光」に向かっていると言えるようです。年譜の最後にもありますように、「もっと光を!」というのがゲーテの最後の言葉だったと言われておりますが、これは実は女中に対して「鎧戸を開けてくれないか、もっと光が入るように」と言った言葉の一部だったのですが、ゲーテの生涯が光を追い求める生涯であったからこそ、そのような解釈が生じたと言えるでしょう。戯曲『ファウスト』の中で、ファウストと悪魔・メフィストが初めて出会った際に、ファウストがメフィストに対して「おまえは一体何ものなのだ」と訊ねます。それに対して、「私は常に悪を欲し常に善をなすあの力の一部分です」という風にゲーテはメフィストに答えさせています。この悪をも善の一部と見做す、言葉を変えれば、悪魔をも神の働きの一部と見做す――「自然全体の肯定」「宇宙全体の肯定」こそが『ファウスト』のテーマだったのではないでしょうか。
1814年(65歳)
ナポレオン敗れ、連合軍パリ入城。ウィーン会議開催。
1815年(66歳)
 8月、ヴィレマー家に五週間滞在。ヴィレマー夫人マリアンネと、ズライカ=ハーテム(『西東詩集』の相愛の男女)のような日々を過ごす。『西東詩集』の多くの作品が成る。
8月、ヴィレマー家に五週間滞在。ヴィレマー夫人マリアンネと、ズライカ=ハーテム(『西東詩集』の相愛の男女)のような日々を過ごす。『西東詩集』の多くの作品が成る。
この『西東詩集』という詩集は、ゲーテの友人である銀行家ヴィレマーの若い妻マリアンネとの交際から生まれました。ゲーテに惹かれている妻に気付いたヴィレマーは、最初は妻をゲーテに近づけまいとするのですが、後に却って二人の仲をとりもつようなことまでやったそうです。われわれ凡人にはなかなか理解の困難な事情があるわけですが、ともかく、『西東詩集』の中から、ゲーテの詩の中でも最も優れたものの一つとされているものとされる『聖なる憧憬』を読んでみましょう。
『聖なる憧憬』 Selige Sehnsucht
賢者のほかには 何人(なんぴと)にも語ってはならぬ Sagt es niemand, nur den Weisen,
凡俗は直(ただ)に嗤(わら)うだけであろう Weil die Menge gleich verhöhnet:
焔にやかれて死を希(ねが)う Das Lebendige will ich preisen,
生きものをこそわたしは讃えよう Das nach Flammentod sich sehnet.
かつておまえが生まれ 今そこでおまえが産みなす In der Liebesnächte Kühlung,
愛慾の夜々の冷気のなかで Die dich zeugte, wo du zeugtest,
蝋燭の灯がしずかにまたたくとき Überfällt dich fremde Fühlung,
ふと あやしい念(おも)いがおまえを捕える Wenn die stille Kerze leuchtet.
おまえはもはや暗黒の片すみに Nicht mehr bleibest du umfangen
じいっと蹲(うずくま)っていることはできぬ In der Finsternis Beschattung,
あたらしい欲情が Und dich reißet neu Verlangen
より高い媾合(まぐわい)へと はげしく心を引き裂く Auf zu höherer Begattung.
どのような遠さにもたじろくことはない Keine Ferne macht dich schwierig,
おまえは引きよせられ 呪法の輪のなかに縛られ Kommst geflogen und gebannt,
夜の蛾よ おまえは灯にとびこんで Und zuletzt, des Lichts begierig,
ついにわが身を灼いてしまうのだ Bist du Schmetterling verbrannt.
死して生きよ! Und so lang du das nicht hast,
この摩訶不思議にふれぬかぎり Dieses: Stirb und werde!
いつまでもおまえは ただ Bist du nur ein trüber Gast
地上の夜の憂鬱な客人(まれびと)にすぎない Auf der dunklen Erde.
訳: 小阪清行
この詩の下線部に注目してみたいと思います。前出の自然哲学者・三木成夫は其角の句「蟷螂の尋常に死ぬる枯野かな」が大層お気に入りだったようで、色々のところで引用しています。この句の意味するところは、ほぼ以下の通りです。「野原に草木の枯れる季節が来れば、蟷螂(カマキリ)の雄は生殖行動を終えた後、雌によってバリバリ食べられてしまう。この残酷な一面も含めて、すべては自然の理(=尋常なる現象)のままに行われるのであって、そこに浅はかな人間の智慧が入る余地はない」。
さて今ここで私は幾分おもしろ半分にではありますが、カマキリと同様「命をかけた交尾」を行った蛾について、「夜の蛾の尋常に死ぬる燭火(しょっか)かな」と言う風にでも詠み変えてみたくなる衝動にかられます。
1816年(67歳)
クリスティアーネ死す。『ファウスト』第二部にとりかかる。
1821年(72歳)
マリーエンパートに滞在、可憐で快活な十七歳のウルリーケを知り、心をひかれる。
1823年(74歳)
マリーエンバートに行き、ウルリーケに会う。ゲーテの情熱いよいよ熾烈。悩み苦しみ、その結果、病的な状態になり、翌年までつづく。
最後に「ゲーテにとって女性とは」というテーマについて話してみたいと思います。先ほど申し上げましたように、この問題を語ることによって、また「ゲーテの自然」を語ることにもなると思うからです。
さて、ゲーテを取り巻く女性というのは実はこの資料に出てくるだけではありません。優にこの倍はいるでしょうか。その中でも極めつけはこのウルリーケの場合でしょう。74歳のジイさまが、小国とはいえ一国の君主であるカール・アウグスト大公を介して、19歳の少女に結婚を申し込み、断られ、病気になって寝込んでしまったというのですから、われわれ世間一般の人間には、一種のグロテスクささえ感じられるのではないでしょうか。
生物の生(ライフ)は「食の生活相」と「性の生活相」に分けられるとありますが、ゲーテの場合、その生涯はあたかも「性の生活相」が途切れずにずっと続いていたような印象さえ受けます。これはわれわれ一般からすれば、自然に反するのではないか、とも思われる訳ですが、フロイトなどが言うように、われわれが不自然にエロスを抑え込んでしまっていることもまた一つの事実なのではないでしょうか。蓮如、一茶、ロダン、ピカソなどのように、精神的に解放された人間がときに見せる晩年の大らかなエロスは、却って人間の秘められた自然性の発現ともとれるような気がしますが、いかがなものでしょうか。
「永遠に女性的なるもの」― 『ファウスト』より
Das Ewig-Weibliche 永遠にして女性的なるもの
Zieht uns hinan. われらを彼方へと導き行く。
訳: 柴田翔
よく言われることですが、ドン・ファンやカサノヴァと違って、ゲーテにとって「女性」は単なる「性(セックス)」の対象ではなく、祈りの対象でもあったのです。ヨーロッパには古くから、マリア信仰や騎士道の女性崇拝などの流れがあり、ゲーテも最もよい意味で、その伝統を受け継いでいるのかもしれません。「永遠にして女性的なるもの云々」は20代半ばから死の直前まで約60年かけて書いた『ファウスト』の掉尾を飾る句なのですが、ここでは女性が救済の原理にまで高められています。しかもかつて自分が愛し、傷つけ、罪に陥れた女性によって救済されるわけです。その女性グレートヒェンのモデルは、実はあのゼーゼンハイムの牧師の娘、フリーデリーケであったと言われています。内村鑑三はファウスト=ゲーテを批判して、「心よりその罪悪を認識してこれを痛切に懺悔したることなし」(参考資料の3-5:
http://www.geocities.jp/seto_no_shorai/3_gakushukai_handout.htm)などと言っていますが、あまり当たっていないのではないかと思われます。
1831年(82歳)
第二部清書完成。『ファウスト』の原稿をまとめて封印する。
1832年(83歳)
22日、永眠。「もっと光を!」が最後の言葉といわれる。柩はワイマルの大公家の暮地にアウグスト公、シラーと並んで安置される。


 8月28日、マイン河畔のフランクフルト市(当時人口三万、重要な商業中心地)に生まれる。父が帝室顧問官の称号をもつ裕福な家。母方の祖父はフランクフルト市長。
8月28日、マイン河畔のフランクフルト市(当時人口三万、重要な商業中心地)に生まれる。父が帝室顧問官の称号をもつ裕福な家。母方の祖父はフランクフルト市長。
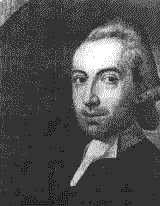 1770年(21歳)
1770年(21歳)
 抒情詩の秀作「五月のうた」、「野ばら」などが生まれる。
抒情詩の秀作「五月のうた」、「野ばら」などが生まれる。
 ぼくは、たぎり落ちる渓流のほとりの丈高い草のなかに臥し、大地に身をよせて数多くの小さな草たちのさまざまな格好を見つめたり、立ちならぶ茎と茎とのあいだにはさまれた小世界のうごめきや、小さな虫や蚊たちの数限りない、見きわめもつかぬ姿をひとしお胸の間近に感じる。また、みずからの姿に似せてぼくたちを造ってくれた全能者の現存、ぼくたちを永遠の歓喜のなかに漂わせ生かしておいてくれる全愛者の息吹、ぼくはそれをひしひしと感じる。 (5月10日)
ぼくは、たぎり落ちる渓流のほとりの丈高い草のなかに臥し、大地に身をよせて数多くの小さな草たちのさまざまな格好を見つめたり、立ちならぶ茎と茎とのあいだにはさまれた小世界のうごめきや、小さな虫や蚊たちの数限りない、見きわめもつかぬ姿をひとしお胸の間近に感じる。また、みずからの姿に似せてぼくたちを造ってくれた全能者の現存、ぼくたちを永遠の歓喜のなかに漂わせ生かしておいてくれる全愛者の息吹、ぼくはそれをひしひしと感じる。 (5月10日)
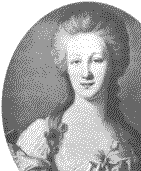
 1776年(27歳)
1776年(27歳)
 1788年(39歳)
1788年(39歳)
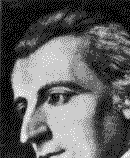 1796年(47歳)
1796年(47歳)

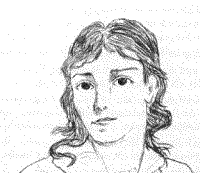
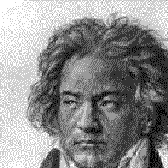
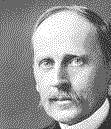

 8月、ヴィレマー家に五週間滞在。ヴィレマー夫人マリアンネと、ズライカ=ハーテム(『西東詩集』の相愛の男女)のような日々を過ごす。『西東詩集』の多くの作品が成る。
8月、ヴィレマー家に五週間滞在。ヴィレマー夫人マリアンネと、ズライカ=ハーテム(『西東詩集』の相愛の男女)のような日々を過ごす。『西東詩集』の多くの作品が成る。
