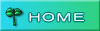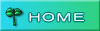三木成夫の生涯と業績
後藤仁敏
講義中の三木成夫氏(1984年7月14日)
[この文章は、「ゲーテ自然科学の集い」(三木成夫自身が発起人の一人)が編集兼発行する雑誌『モルフォロギア ― ゲーテと自然科学』第16号(1994年11月3日発行。発売元・ナカニシヤ出版)に発表されたものです。ホームページへの転載にあたっては、著者の後藤仁敏氏および『モルフォロギア』編集委員会から承諾をいただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。なお、後藤氏の原稿はワープロ専用機で打ちこまれていたため、「三木成夫の会」事務局で入力しなおしました。それゆえ入力ミス等に関する責任は「三木の会」事務局にあります。]
はじめに
恩師・三木成夫が亡くなってからはや七年が過ぎた。この間、三回の三木成夫追悼・記念シンポジウムが開催され、藝大で追悼展や追悼音楽会がおこなわれ、著作では『三木成夫追悼文集』をはじめ、『生命形態の自然誌・第一巻、解剖学論集』、『海・呼吸・古代形象』、『生命形態学序説』が次々と出版された。
そのなかで、私も、記念シンポジウムのひとりとしてその運営にたずさわったり、また、すぶすな書院の編集者からの依頼で、遺稿集の校正を手伝い、とくに『生命形態学序説』の巻末につけられた三木成夫原図シェーマの解説を執筆したりした。
私と三木氏との出会いから、氏から学んだことについては、すでにいくつもの文に書いてきた(1)。ここでは、三木氏の生涯をふりかえり、その思想の形成過程について考察し、残されたいくつもの業績について紹介したい(以下敬称略)。
つぎに、三木成夫の生涯を(一)丸亀・岡山時代、(二)学生時代、(三)本郷(東大)時代、(四)お茶の水(医歯大)時代、(五)上野(藝大)時代、に区分して紹介する。このような時代区分は、平光厲司氏(2)にしたがったものである。
[注]
(1) 三木成夫について書いた拙文には次のようなものがある。
「三木成夫先生を偲ぶ」(地学団体研究会機関誌『そくほう』406号 8頁 1987)
「三木成夫先生を偲ぶ」(『三木成夫追悼文集』追悼文集編集委員会 1989 60―62頁)
「三木成夫先生に学んだこと」(『生命形態の自然誌・月報1』うぶすな書院 1989 3頁)
「三木成夫の原点と到達点・書評『生命形態学序説』」(モルフォロギア 第15号 1993 100―103頁)
「三木成夫と手塚治虫の比較人間論」(『現代思想』1994年3月号 191―203頁)
(2) 平光厲司「あとがき」(『生命形態の自然誌・第一巻』1989 471―474頁)
(1) 脾臓と血管系の比較発生学的研究
(2) 「解剖生理(解剖学ノート―人体の歴史を中心にして)」
(3) 「ヒトのからだ―生物史的考察」
(4) 古生物学との出会い
(5) 医歯大での解剖学総論と解剖実習
(6) 「解剖学総論草稿」―人体解剖学から宗族発生へ
(1) 藝大への転勤―現代科学の岐路にたって
(2) 「生命形態学」の執筆
(3) 「動物的および植物的―人間の形態学的考察」
(4) 宗族発生的・クラーゲス的保健論
(5) 「脊椎動物のPhylogenie―人頭骨の“なりたち”に関する考察」
(6) 『内臓のはたらきと子どものこころ』
(7) 『胎児の世界―人類の生命記憶』
(8) 「南と北の生物学」
(9) 死の状況
(1) 追悼の行事
(2) 『生命形態学の自然誌 全三巻』
(3) 三木成夫記念シンポジウム
(4) 『海・呼吸・古代形象―生命記憶と回想』
(5) 『生命形態学序説―根原形象とメタモルフォーゼ』
(6) 広がる三木成夫の世界
三木の略歴年表と主要著作を以下に示す。
小論をまとめるにあたり、表Ⅰに示した三木の著作のほか、『追悼文集』や幾度も行われた偲ぶ会での参加者の発言、その他の資料を参考にした。とくに、三木桃子・塚本庸夫・今井健一・向川惣一の諸氏には、貴重な資料を提供していただいたり、ご意見を賜った。これらの方々にこころより感謝する次第である。
稿を終えてみれば、小論は、三木の生涯と業績についての素描に終わってしまったといわざるをえない。三木の業績は、さまざまな分野にわたっており、今後さらに多方面から研究される必要がある。また、三木の思想についても、ゲーテ、クラーゲス、冨永半次郎までさかのぼって、深く探求されなければならない。小論は、三木の業績の広さと思想の深さをあらためて明らかにしたものにすぎない。
二十年にわたるかぎりないご教示と、こころ暖まる励ましに感謝して、小論をあらためて雲の上の恩師・三木成夫に捧げたい。
(ごとう まさとし・解剖学/古生物学)